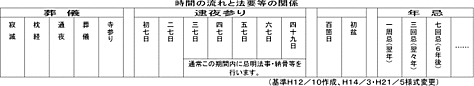ページ内コンテンツ
葬儀・年忌等の流れ 
昔は親戚の中に一人位は仏祭りやしきたり等に詳しい方が居て、葬儀や法事の場に直面しても良きアドバイス得ることが出来たのですが、最近はその方面に通達された方が居る場合のほうが珍しいのかも知れません。
土地土地により葬儀や年忌供養などの流れや、作法は異なる所です。
文字にすることには多少抵抗がある所ですが、法雲寺で執り行っている葬儀や年忌等の流れや留意事項についてご説明します。
葬儀の流れ 
「生ある者の掟」。誰しも夫々に定められた死辰が何時かは訪れます。残された親族にとってはその別れは簡単には受け入れ難く、悲しみを癒すには相当な時間を要することで有ろうと思います。
しかし、再び語らぬ故人に対して何時までもすがるのではなく、その「愛別離苦」の苦しみを乗り越えては敢えて多くの人々の前で別れを告げ、体が束縛していた魂を解放し、極楽世界や、次なる生の世界へと旅立たせて上げるのが葬儀の意味する所かと考えています。
そのことにより、故人の次なる生に良い縁が授かり、また、葬儀という儀式を執行することにより、残された人々の別離の悲しみが追慕の念へと変わっていくのかもしれません。
枕経 
- 村岡周辺であれば、零位がご自宅にお戻りになった頃、枕経にお伺いします。
- 通夜・葬儀の時間をご相談の上、決定させて頂きます。
- 役僧・諷勤僧などのお手伝いの僧侶が必要な場合は、お伝え下さい。
- 遠方の場合、枕経に参上できない場合がありますが、ご了承下さいます様お願いします。
- 作成の為の用紙をお渡ししますので、通夜終了までに分る範囲で記入をお願いします。→
- お授けする「戒名」に入れたい文字等有りましたら、ご相談下さい。
通夜 
- 葬儀の前夜に通夜のお勤めを行います。
- 通夜の所要時間は約40分程度、参列者の焼香人数により前後します。
- 通夜のお勤め終了後、村岡周辺の場合、喪主が参列者に向かってご挨拶をなさいます。
- 地域によっては通夜を行わないところもあります。
葬儀(剃度式・告別式) 
- 村岡周辺での葬儀の場合は、荷物がたくさんある関係で送り迎えをお願いします。
- 葬儀法要時間の目安は約1時間ですが、焼香人数・弔辞の有無等により時間は変わります。
- 式前半の剃度式では、仏弟子となった故人に戒名(法名)をお授けします。
- 式後半の告別式(引導式)では、前日記入して頂いた用紙を元にとして、故人の人となりを読み上げさせて頂きます。
お寺参り 
- 村岡周辺の場合、火葬場が近くに有った頃は、火葬から集骨の間にお寺参りにお越しになりましたが、最近は火葬場が遠くなった関係で集骨が終わった後に、お骨と共にお寺参りにお越しになる方が増えています。
- 遠方の方は、後日都合が会う時にお越し下さい。
初七日 
- 当地方では初七日は初七日当日ではなく、「逮夜」として初七日の前夜にお勤めをする場合が一般的です。
- 逮夜の数え方は、寂滅日の1日前から数えて7日目の夜になります。
- (例:10日にお亡くなりになった場合は、9日から数えて7日目(9・10・11・12・13・14・15)の15日の夜が初七日の逮夜になります。)
- 逮夜表印刷ワークシート →
 逮夜表.xls (マクロを使用しています。うまく動かない場合はご勘弁)
逮夜表.xls (マクロを使用しています。うまく動かない場合はご勘弁)
- 遠方での葬儀や、親族が集まりにくい場合など、葬儀当日の集骨後に初七日を行われる場合も有ります。
- 村岡周辺では初七日にはお世話になったご近所の方にも集まって頂き、喪主が逮夜の席でご挨拶をなさいます。
以降の逮夜 
- 初七日から7日(一週間)ごとに、忌明法事を行うまで、塔婆を建てて逮夜参りを行います。
- 初七日以降の逮夜は親族・家族だけが集まる場合が多いです。
- 村岡周辺の場合、基本的に忌明法事まで逮夜参りに住職が参上させて頂きます。
忌明法事 
- 昔は満中陰(七七日忌・49日・七逮夜)で忌明としていましたが、最近では五七日忌(35日)・三七日忌(21日)で忌明法事をされる所も多いようです。
- 忌明法事までに仏壇に収める位牌を準備し、お墓が有る場合には墓碑に戒名を刻んでおきます。
- 忌明法事後は新霊檀を片付け、ご位牌は仏壇に収めて普段の生活に戻ります。
納骨 
- お墓のご準備が整っている場合、忌明法事の後にお墓に向かい納骨をされる方が多いですが、四十九日や百日忌までご自宅でお祀りされた後、納骨される方も居られます。
- 納骨は
- 骨壷のままお墓に収める
- 壷から出して直接お墓の中に収める
- 壷から出して、さらしの袋に入れて収める
等、土地や各人の考えで様々な方法があるようです。
- 納骨の時には、葬儀以来の各種塔婆や白木の位牌、香炉等もお墓に持って行き、次のお墓参りまで暫らくお墓にたてておきます。
- 村岡周辺では納骨後、骨壷は墓地で細かく割り、墓地の片隅に埋めるのが昔からの慣わしです。
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | ご供養について/葬儀・年忌等の流れ |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | admin |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | なし |
| ユーザー : | なし |
Counter: 4052,
today: 1,
yesterday: 0
初版日時: 2010-01-10 (日) 11:44:08
最終更新: 2010-01-10 (日) 17:55:41 (JST) (5668d) by admin